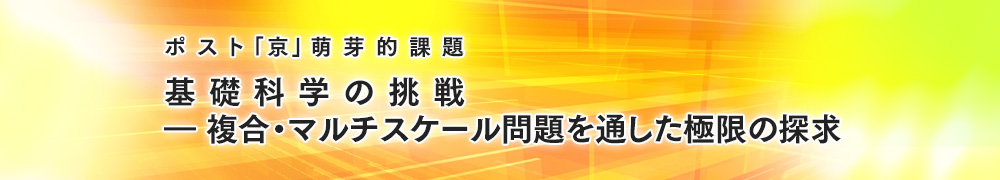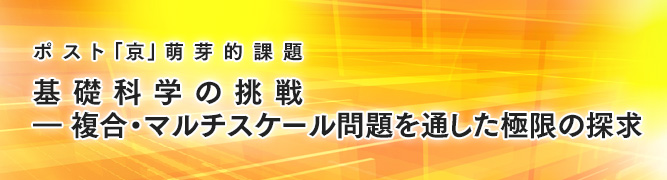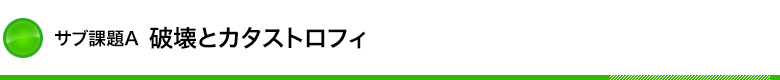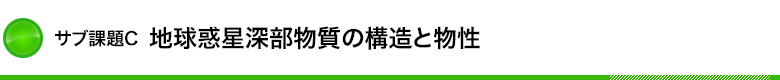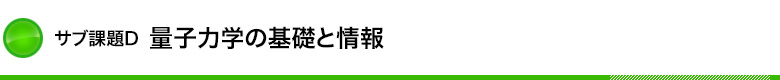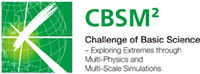サブ課題概要
研究開発内容:
ポスト「京」により、これまで不可能であった破壊とカタストロフィ、相転移と流動、地球惑星深部物質の構造と物性などに関する異なる階層をつなぐ複合・マルチスケール問題に対して、計算精度・計算可能性の限界突破に挑戦する汎用的手法を開発するとともに、大規模シミュレーション・高精度シミュレーションを実施することにより、学際連携を通して、これら複合・マルチスケール問題の解決を実現する。主要な参加機関である東北大学金属材料研究所、東京大学物性研究所の共同利用スーパーコンピュータも併用しつつ、以下のA~Dのサブ課題を設けて研究開発を推進する。
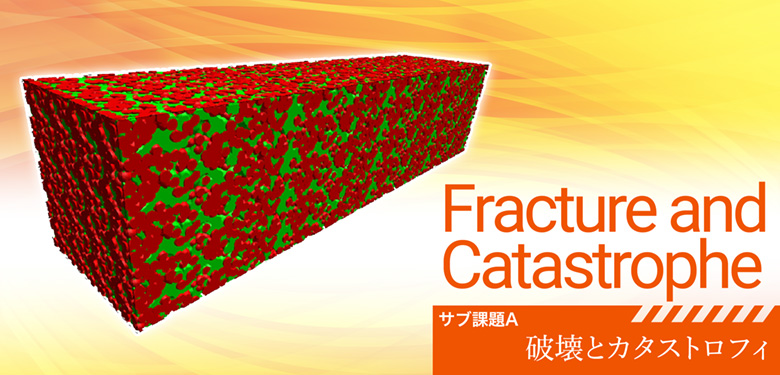
サブ課題代表者:東北大学金属材料研究所 久保 百司
 |
材料の破壊は人工構造物の破壊をもたらし、断層の破壊は地震となり、人間の生命を脅かすカタストロフィとなる。本課題は、電子・原子レベルから数100kmオーダーに至る材料および断層破壊現象の階層性とそのメカニズムの解明を、原子レベルの材料破壊メカニズム研究と地震メカニズム研究の学際連携により進める。 |

サブ課題代表者:東北大学大学院理学研究科 川勝 年洋
 |
ナノバブル形成と微小成分添加効果、雲の形成過程、機械流動中での気泡・液滴生成過程、マグマの流動、高分子・コロイド流動、バイオ流動など自然界に幅広く観測される多相共存構造を持つ混相流を対象として、マルチスケールの流動シミュレーション用プラットフォーム(MSSP)を開発し、超並列大規模分子動力学シミュレーションとの比較検討および上記の具体例への適用による方法論の検証を行うことで、未知の複雑流動に対してそのマクロな特性をミクロなモデルを用いて予測する手法の開発を目指す。 |
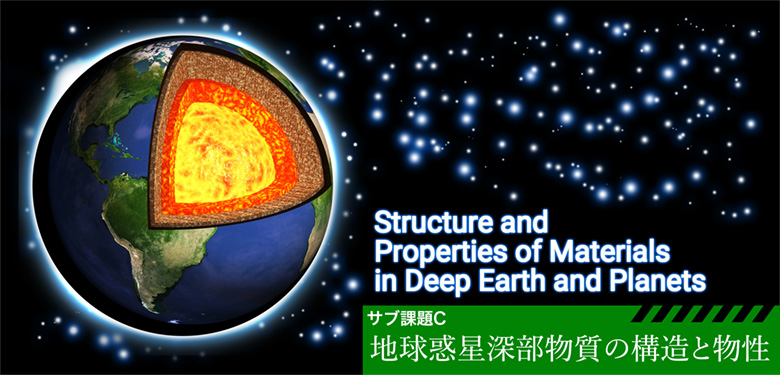
サブ課題代表者:理化学研究所 飯高 敏晃
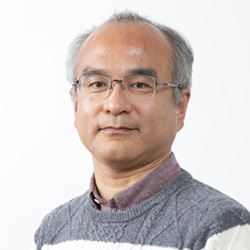 |
地球深部を構成する珪酸塩・液体鉄・固体鉄などの物質の極限環境下での振る舞いはまだ良く分かっていない。電子・原子のミクロな視点に基づく超大規模第一原理計算によりこれらの複雑な物質の性質を決定し、高圧実験や地球科学の専門家と連携することにより、地球の誕生から現在・未来までの歴史をマクロに理解するための基礎を築く。 |
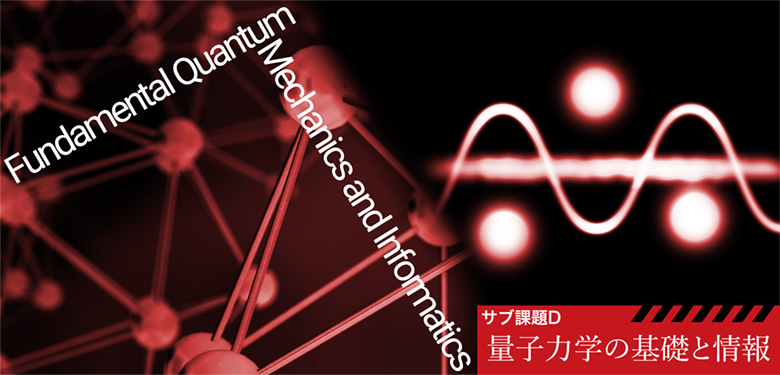
サブ課題代表者:東京大学物性研究所 川島 直輝
 |
量子力学の創始以来の夢であった量子力学的多体問題の一般的手法を開発し、従来計算不可能であった問題を解決するため、物質科学、素粒子論、応用数理、量子通信の諸分野の連携によって、テンソルネットワーク法、ウェーブレット法、行列ベクトル積型計算手法などに基づく新しい並列化アルゴリズム/コードを開発し、その諸分野における応用例を示す。 |